ヤマハ音楽教室の講師には、さまざまなジャンルの音楽に精通し、歌唱、鍵盤レパートリー、アンサンブル、ハーモニーや創作など、多くの音楽要素を扱う高い音楽力が必要です。講師のキャリアは講師資格試験に合格することからスタート。合格後は各種講習を受講し、レッスンシュミレーションや教材研究、レッスン実習等を行って各コースにおける指導方法を習得、複数の子どもたちの個性や意欲を尊重した幅広い指導力を身に付けます。また、長期的なキャリアアップのための制度も用意され、より良いレッスンをご提供できるよう、講習・勉強会等を受けながら、常に自己研鑽を続け、指導力向上に努めています。

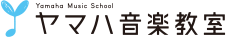













 もっとくわしく
もっとくわしく






 ヤマハ音楽教室公式アカウント
ヤマハ音楽教室公式アカウント